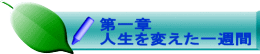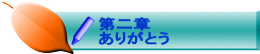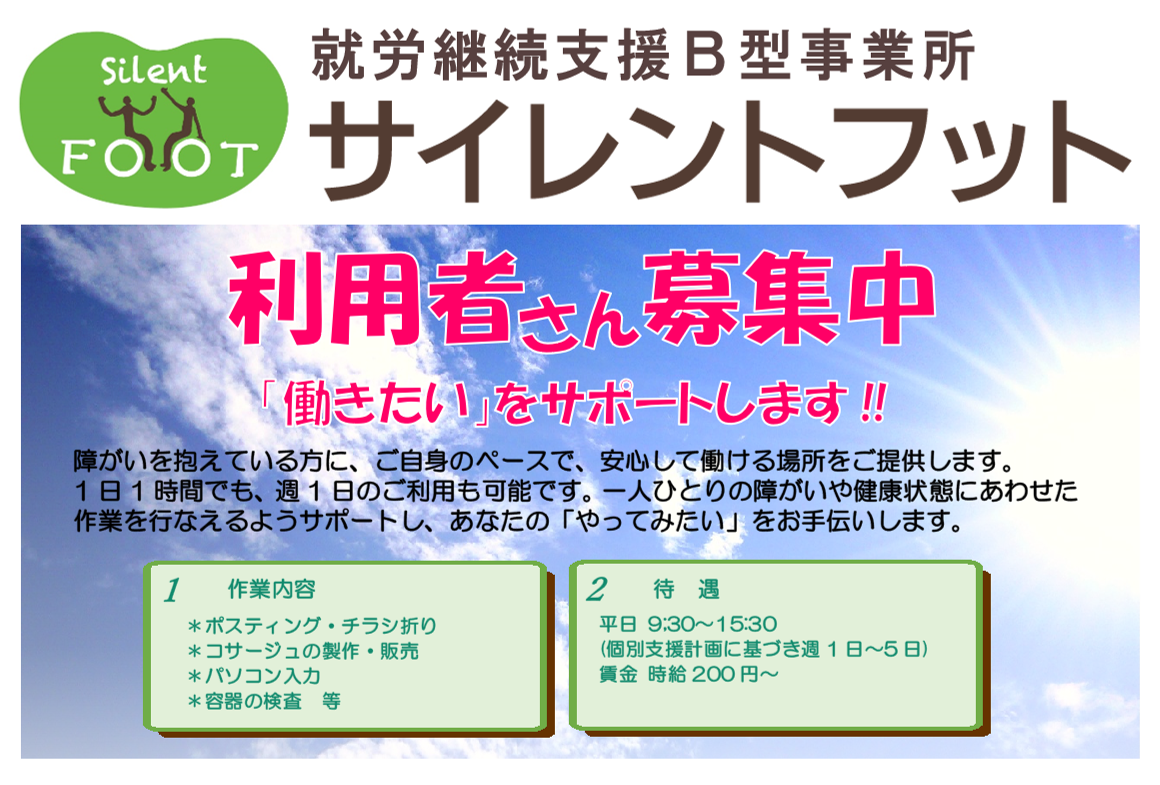第一章 「人生を変えた一週間」
(6月21日)
朝から入院を決意して病院に向かおうとする。
すでに自力で玄関まで行くことも、車椅子に乗ることも出来なくなっていた。
200メートルほどの病院がまるで遠く離れた異国に感じられる。
「入院すれば楽になれる」
そう信じて、救急車を呼び、車でほんの1・2分の所に在る病院に向かった。
病院に着き医師が私の状態を見るなり、「緊急の検査が必要だがここの病院では設備が無いので大学病院に行って下さい!」と言われた。
すぐに紹介状を書いてもらい、再び救急車で運ばれて北里東病院に向かった。
病院に着くと慌ただしくストレッチャーのまま検査室に運ばれた。
「こちらのベッドに移動出来ますか?」と聞かれて「無理です!」と私は即答した。
身長183cm、体重88kgの身体はとてつもなく大きく、重く感じた。
検査室に入ると間もなく2人の医師が私の前にあらわれた。
医師が私の症状について話し合い、麻痺の原因を見立てた。
「脊髄にポリープが出来て神経を圧迫しているんだろ!?」
「切除すれば一週間位で歩けると思いますよ」とK医師が軽い口調で言った。
「切除?切るんですか?」と聞き返すと「そうだねっ」と軽く返された。
「手術はいやだ!」心の中でそう思った。
検査をするためベッドごとMRI室に運ばれる。
MRI検査は閉所恐怖症の私にとって過酷なものだった。安定剤を呑み、パニックが起きたら出してもらうことを約束して棺桶の様な検査機に渋々入る。
安定剤の効果もなく、私は3回も助けを呼び検査を中断させた。通常40分程で終る検査だが1時間以上も時間が経過していた。情けない話だ!
一通りの検査を経て病室へ行く。
入院は初めての経験で、手術と聞いた動揺は隠しきれない。
「これからどうなるのか?」不安が頭の中を巡っていた。
病院の消灯時間は22時、「早いな~」と思いながらテレビを消すと直ぐに睡魔がおそってきた。
ここ数日の慌ただしい出来事で満足に寝ていなかった私は、入院した安心感と今頃になって効いてきた安定剤のせいか、いつの間にか深い眠りについていた。
(6月22日)
朝目が覚めると、昨日までかろうじて動いていた右足もすでに思うように動かす事が出来ず、右足の親指が少し動く程度になっていた。
自由を失い、ただベッドの上でこれからの自分のことを考える。
「いつ手術をするんだろう?」
「いつになったら歩けるんだろう?」
「早く仕事に戻らないと!」など復帰することばかり考えていた。
フッと今の状態に気付くと、尿道にはカテーテルが突き刺さり、その先には尿を貯めるバックが付いている。
ベッド上の自分は、自ら寝返りも出来ず、支え無しで座ることも出来なかった。
トイレもベッド上で済ませていた。
足に神経が無いと言う事が、全身に様々な影響を及ぼして、今まで当たり前に出来ていた事が出来ない、まるで自分の体が何かに支配されてる様だった。
その現実に気付くと「歩けなくなるのでは?」と言う不安も頭を過った。
昨日の検査結果が気になっていたが、医師からは何の告知も無いまま消灯時間を迎えた。
(6月23日 宣告の日)
今朝は不安と苛立ちで4時に目が覚めた。
早起きは三文の得と言うが、今の私には何の得も感じず、ただ不快な朝としか言い様がなかった。
電動ベッドを起こし、唯一自由に動く手でお世辞でも美味しいと言えない朝食を口に運ぶ。
病院から出された訳の分からない薬を呑み、検査結果の報告を待ち、時間が過ぎていく。
家族、友人、会社のスッタフ、看護士、沢山の人たちが病室を出入りする。
人と話してるうちは気が紛れ、表面上は笑いながら話をして冷静をよそおっていたが、心境は不安でいっぱいだった。
面会時間が過ぎ、夕食を済ませると病室が静まり返る。
独りになると孤独を感じ不安と苛立ちを感じる。
今日も医師から何も言われない・・・。
消灯時間が近付く頃、看護師長が巡回で病室を訪れ、私の体の寝返りを介助をしてくれる。
私は、看護師長に訪ねた。
「手術は、何時やるんですか?」
看護師長は言葉を濁らせた。
その後も私は不安な心を隠すかの様に、自分の生い立ちやこれからの目標などを看護師長に話し続けた。
そして、一番聞きたく無い不安な思いを口にした。
「このまま歩けなくなるって事は、無いですよね?」
その言葉に看護師長は「・・・、ちょと待って下さい。」そう言い残し病室を後にした。
5分程して担当のK医師が訪れた。
「先生、僕の足はどうなるんですか?」
K医師「詳しいことは後日お話ししますが・・・、佐藤さん、貴方の足が動く事は・・・、無いでしょう・・・。」
何も言えなかった。
ただ「嘘であって欲しい、夢であって欲しい」と祈った。
頭が医師の言葉を否定し、現実を受け入れることが出来ない。
私は心の中で叫んだ!
「冗談じゃね~!」
医師が去り、様々な事が頭の中を駆け巡った。
独りで居るのが怖く感じる。
看護師長は、その気持ちを察した様に黙って側にいてくれた。
胸に何かが詰まり、息苦しく感じる。
やがて一筋の涙が頬を伝わり落ちると、体が震えて涙がとめどなく流れた。
毛布で隠れた自分の足を見ることも出来ず、毛布の上から麻痺した足を撫でた。
その手には、しっかりと足の存在が感じられる。
人生の40年間を支えてくれた両足が意図惜しく思えてならない。
「なぜ?…どうして?」
涙はいつまでも流れ続けた。